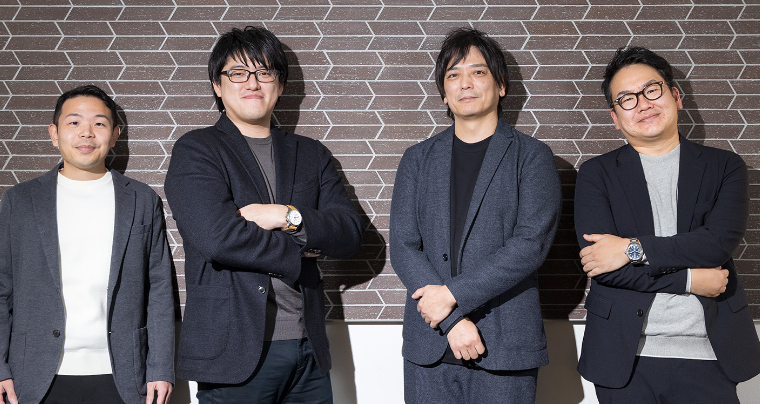
【ガバメント】
類似性構造分析に関する調査研究に、公共セクターチーム×先端技術チームのシナジーで臨む


変化するビジネス環境に対応するため、従来の古いシステムや業務フローを見直す必要に迫られている企業は少なくないと思います。しかし、大きな組織ほど、さまざまなレイヤーで刷新に向けた合意形成に時間と労力がかかり、推進の難易度が上がります。どのようなロードマップを策定し、どのようなアプローチを取れば良いのでしょうか?
金融機関のシステムと業務の改善を支援するKPMGコンサルティングの4名が、組織の変革にどのように取り組んでいるのかを語りました。

変化するビジネス環境に対応するため、従来の古いシステムや業務フローを見直す必要に迫られている企業は少なくないと思います。しかし、大きな組織ほど、さまざまなレイヤーで刷新に向けた合意形成に時間と労力がかかり、推進の難易度が上がります。どのようなロードマップを策定し、どのようなアプローチを取れば良いのでしょうか?
金融機関のシステムと業務の改善を支援するKPMGコンサルティングの4名が、組織の変革にどのように取り組んでいるのかを語りました。





クライアントは金融機関で、システム改善と業務改善を支援するプロジェクトでした。もともと、複数の会社が15年ほど前に合併して1つの会社になったという経緯があり、各社のシステムや業務遂行体制の大部分を残したまま合併したため、個々のシステムが独立しサイロ化してしまっている、という課題がありました。30年、40年使い続けているレガシーシステムもあり、不具合が発生する都度、「部分最適」化して改修を重ねていました。その結果、システムがどんどん肥大化し、複雑化していました。

もともと、今回のプロジェクトに先立ち、2019年に同社のIT戦略策定を支援しており、「クラウド」「デジタル化」「システムの刷新」の3つの柱を掲げ、その後1年半ほど、前者の2つに注力し情報提供などをしていました。そして2023年から新たに始まった今回のプロジェクトでは、3つ目の「システムの刷新」をターゲットとし、それに伴う業務改善の支援も行うことになりました。開始して1年半が経ちますが、現在は、クライアントの社員がどのような悩みに直面しているか情報収集を行い、今後の改善施策の方向性を策定していく、というフェーズです。要件定義が終了するのがここからさらに2年後という、かなり長丁場のプロジェクトです。

金融機関の営業支援システムなどは、窓口で対面する行員の使いやすさも考慮され、新しいシステムへの入れ替えが進む一方、その裏側で動く基幹系システムは長く同じものが使われ、残り続ける傾向にあります。融資をするための手続きや、利息の計算といった仕組みはあまり変わらないですからね。

システムの刷新の遅れというのは、同社に限らず、日本の金融業界全体の課題なのかな、と感じています。そういえばK. Uさんは第二新卒でKPMGコンサルティングに入社し、前職が金融業界ですが、現場ではどのように感じていましたか。

確かに、総じてデジタル化の遅れは感じていました。このプロジェクトには2024年の7月から参画していますが、クライアントの状況を伺う中でも、こうした状況を放置することで、今後、長期的に業務効率の低下やサービス品質の伸び悩みが発生する懸念を感じます。システムの抜本的な改善には、早期に取り組むことが重要だと思います。

私もK. Uさんと同じく中途入社で、このプロジェクトがスタートして1年ほど経ったタイミングで参画しました。前職もコンサルティングファームだったのですが、その時のことを振り返ると、今回のクライアントのような組織改革のニーズは多かったですね。

私が2019年から、R. Fさんが2023年から、そして2人が2024年から参加していますが、この4人の他にもメンバーがいて、総勢11名で遂行しています。KPMGコンサルティングが支援している中でも、かなり大掛かりなプロジェクトだと思います。

まずは、クライアントの置かれている現状をしっかりと把握し、具体的にどのような方向を目指して刷新していくのかを模索することが大事です。クライアントが感じている課題を詳しくヒアリングすることに加えて、金融機関であれば、新たな制度や法律、規制緩和の動きにも影響を受けるため、外部環境の分析も実施しました。

私はプロジェクト全体を統括する立場として、経営層を含めたマネジメント層の方々がいかに刷新に向け本気になっていただけるか、コミュニケーションの設計に時間を使いました。具体的な改善プロセスを頭で理解いただくだけでなく、「共感」を得るところまで持っていかなければなりません。先方の経営層やマネジメントの皆さんとは、膝詰めでかなり密にコミュニケーションを取りました。
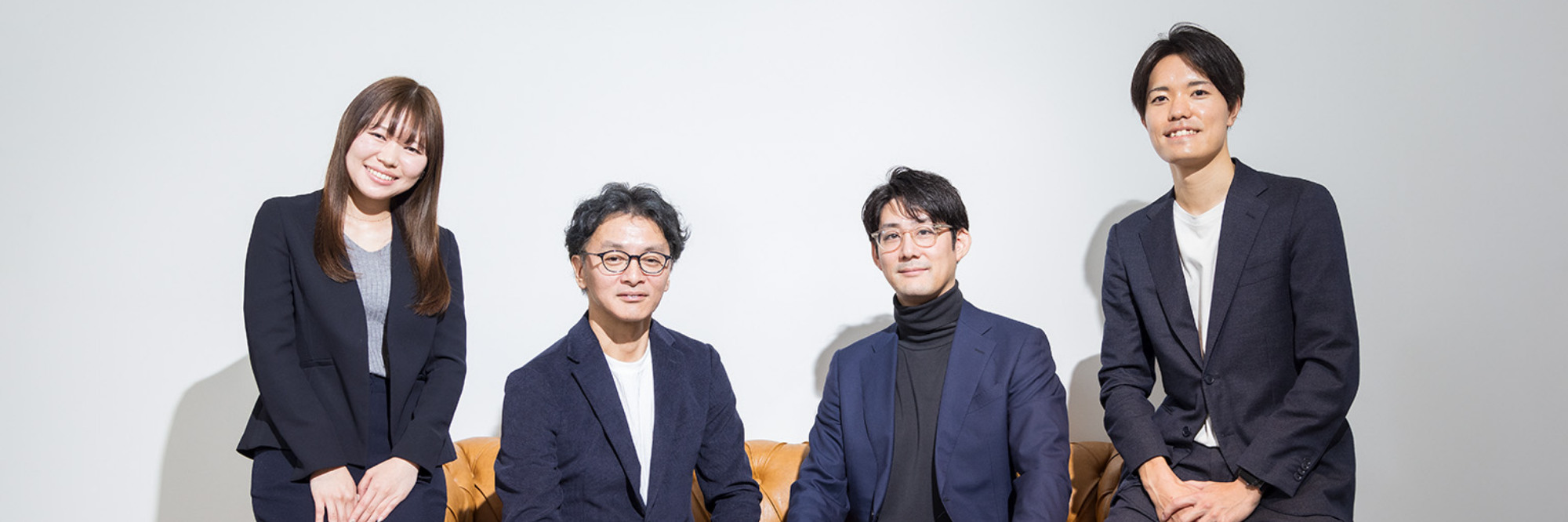

まさにそれが一番難しいポイントだと思います。

もともと別の組織が合併してできた企業ですので、いきなり「システムや業務プロセスを共通化しましょう」と呼びかけてもその意義はなかなか浸透しません。我々は、「業務」と「システム」の2軸で改善の支援を行っていますが、業務とシステムはそれぞれが独立しているものではなく、双方向に作用するものです。そのため、システムを利用する側の目線やシステムを管理する側の目線、さらには経営層の目線など、さまざまなレイヤーから呼びかける必要があると思います。社員の方の意識を「共通化」に持っていくためには、トップダウンで上から押しつけるだけでも浸透しませんし、ボトムアップで現場だけ意識が高まってもダメで、それぞれに異なったアプローチを、同時並行で進めることが求められます。

私はシステム刷新のチームでクライアントとのやり取りを担当していました。主にボトムアップ型のコミュニケーションが多かったかなと思います。システム開発を担当されている方は各事業部におられるので、その方々と、こちらの仮説をぶつけながら、現行の仕様がどうなっているか、どこをどう刷新したいか、といった意見を取りまとめました。全体のマイルストーンが決まっているのですが、それに合わせて最初に各タスクの細かなスケジュールを立て、クライアントと打ち合わせを設定していくイメージです。やはり、大規模で、関係者が非常に多いプロジェクトならではの難しさはありました。

私も、関係者が多いという点は非常に難しいと思っています。ただでさえ複数の組織がベースとなっていることに加え、関係者が業務側とシステム側に分かれていて、その双方に、今回のプロジェクトに対する温度感や、意識のギャップがあります。幅広く意見を聞きながら全体の方向性をまとめ上げていくというコミュニケーションは、まだまだ試行錯誤の途中です。

いきなり「これが正解です」と提示しても相手は受け入れづらいものです。今の状態だったら相手はどれくらい受け入れていただけるか、どのようにマインドチェンジしていけるかなど、日々のコミュニケーションの中で探りながらのやり取りが求められると思います。

また、確定できない要素がある中で、仮の状態をベースに置き、進めていかなければならない場面が多かったのも難しいポイントでした。何が決まっていて何が決まっていないのか、何がわかれば決まるのか、誰と合意すべきなのか、といった要素を整理し、少しでも話が前に進むように意識してファシリテーションしていました。

外部からの支援という立場を活かし、クライアントの中で、「他の事業部には直接言えないけれど、KPMGコンサルティングになら言える」という関係性を作っていくことも大事です。遠慮されないように、潤滑油となる役割を意識的に担っていくこともポイントかと思います。

同時に複数のタスクが進行しているので、我々のチーム内での密な情報共有も心がけており、プロジェクトメンバー総勢11名が風通しよくやり取りができていると思います。以前、私が親族の弔事で1週間ほど抜けなければならなくなり、その旨をクライアントの役員の方にお詫びしたところ、「KPMGコンサルティングはいつもチームで対応してくださっているので、全く心配していません。しっかりお見送りしてきてください」と言っていただいたんです。チームワークを評価していただけたのは嬉しかったですね。私自身も、このプロジェクトを通じてチームが大きく成長しているのを日々感じています。


KPMGでは、「KPMG Connected Enterprise」というグローバル共通のアプローチを開発しています。クライアント社内のそれぞれの部門から、クライアントの先にいるお客様まで、すべてのステークホルダーの期待に応えながら、顧客起点で一気通貫して変革していくアプローチです。これまで、「組織変革」というと、自社目線に終始していることが多かったと思いますが、ビジネス環境は変化し、企業経営におけるサステナビリティへの意識が不可欠になってきています。「KPMG Connected Enterprise」は、社会を起点として考える、という組織変革を前提としたアプローチです。

また、これはグローバルで定義されたアプローチであり、これを大きな指針としながらも、実際に我々がクライアントへ提案する際には、日本企業の実情とギャップがないよう調整しています。

KPMGコンサルティングには、「現行踏襲を良しとしない」という価値観があるように思います。これまでもこうしてきたから次もこうする、ではなく、クライアントの本来のあるべき姿を考えて提案していく、ということを経営層もマネジャー層も大事にしており、企業文化としてかなり浸透していると感じます。

私は、入社した時に宮原社長が「KC(KPMGコンサルティング)ファンを作っていきたい」と言っていたことが印象に残っています。売り上げを追い求めることが至上命題なのではなく、クライアントの健全な成長に貢献し、KPMGコンサルティングを選びたいと思っていただけることが大事、という考え方で、そこが競合他社とは違うポイントなのかな、と思います。前職もコンサルティングファームだったので、よりその違いを感じます。クライアントにとって何が一番良いかを常に考えられる環境だと思います。

K. Uさん、K. Hさんが今言ったように、KPMGコンサルティングが大事にしているのは人だと思います。クライアントの企業風土や価値観を真摯に受け止め、多様性を尊重しながらコラボレーションをしていくことが大切にされています。

コンサルティングのサービスにおいて提供できるソリューションそのものは、どの会社も実は大きく変わりません。だからこそ、クライアントにバリューを感じていただけるとしたら、人の要素となります。まずはクライアントの経営方針、ビジョン・ミッション等、社会に対してどういう価値を提供していきたいのかを理解します。その上で、人と人との関係を大切にしながら、オーナーシップを持ってしっかり寄り添っていくのが、我々の特色だと思います。


今回のクライアントは、災害やパンデミックなどの有事の際、被害に対処するために必要な金融支援を行うなど、金融機関の中でも特に社会性が高い企業であることが特徴だと思います。そういったクライアントの課題に寄り添うことは社会貢献にダイレクトにつながることですし、大きなやりがいがありました。私は前職がSEなので、システムに携わるという点はあまり変わらないのですが、コンサルティングの仕事は、より組織の構造や、人のマインドにまでかかわれることができるのが面白い点だと思います。

金融機関というのは、私たちの社会の中ではインフラのようなものです。少しでもシステムに問題が出ると、社会全体に影響を及ぼします。だからこそ、変わっていくことに対して怖さを持ったり、慎重になったりということは当然あるでしょう。我々は、その点を理解しながら、長い目で見て変革を進めていかなければなりません。クライアント社内の価値観の違いを打破していくことは難しいながらやりがいを感じますし、我々一般市民の生活に欠かせないインフラを改善していくという点にも、意義を感じることができました。

業務プロセスの改善や、組織変革の分野では、現状(As-Is)と目指すべき姿(To-Be)を提示し、両方を比較して進行していく必要があります。まずはクライアントのことをしっかりと理解するために、業務マニュアルをとことん読み込みました。合併前の組織の名残で、業務マニュアルがいくつもあったので、すべて目を通して理解するのはなかなか大変でした。でも、それができないと、「業務をよく理解しないまま提案してきている」と思われてしまうかもしれません。そのような大変さの一方で、クライアントの文化にどっぷり浸かって、並走して同じ課題に取り組んでいくというのは、熱意ややりがいを持って取り組めることだと感じています。また、経営課題に直接アプローチできるのは、コンサルティングという仕事の魅力的な点だと思います。

私は、T. MさんやR. Fさんとは違い、プロジェクトに参画したのがここ最近なので、クライアントの中で、ある程度の合意形成が終わった段階だったのかもしれません。それでも、参画した当初は、議論が多方面に散らかりがちでしたが、今ではさらに合意形成が進み、大きな変化を感じますし、日々アウトプットを出す中でも「よかったな」と実感することが増えました。クライアントからも感謝の言葉をいただくこともあり、やりがいを感じ、頑張ってよかったな、と思います。

最初は「(システムや業務プロセスの)共通化」という言葉を出すだけで拒否感を示していた方々も、徐々に時間をかけていくうちに、それが今回のプロジェクトが目指す姿として浸透していくのを感じましたよね。

K. Uさんが、膨大な量の業務マニュアルを読み込んだと言っていましたが、そういった一つひとつのタスクは、すごく地味で地道なこと。しかし、そういった業務一つひとつに「社会的な意義」を感じながら働けるのがコンサルティングの魅力だと、僕は長年この仕事をやっていて思います。
※記事の記載内容は2024年12月時点のものとなります。