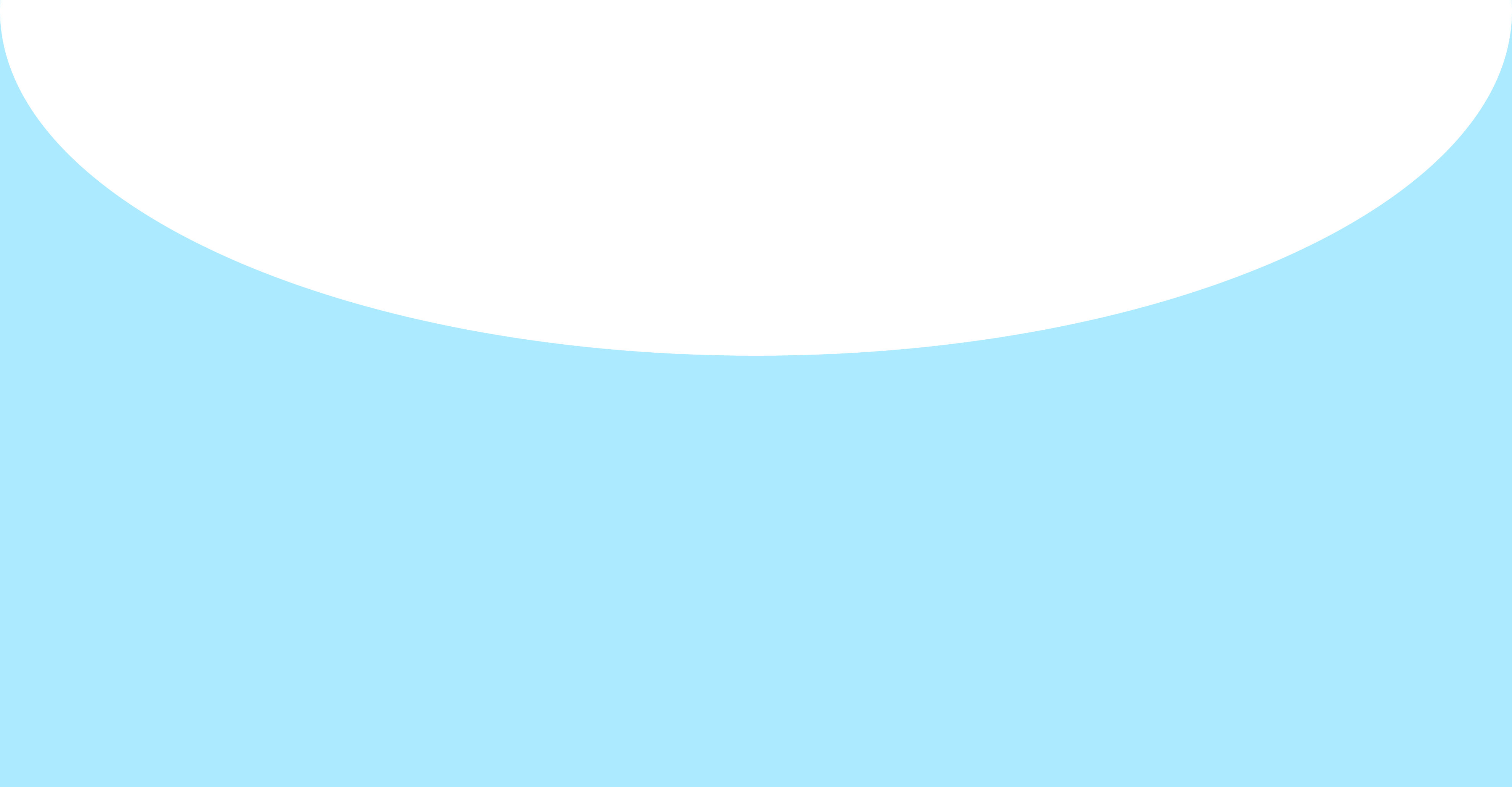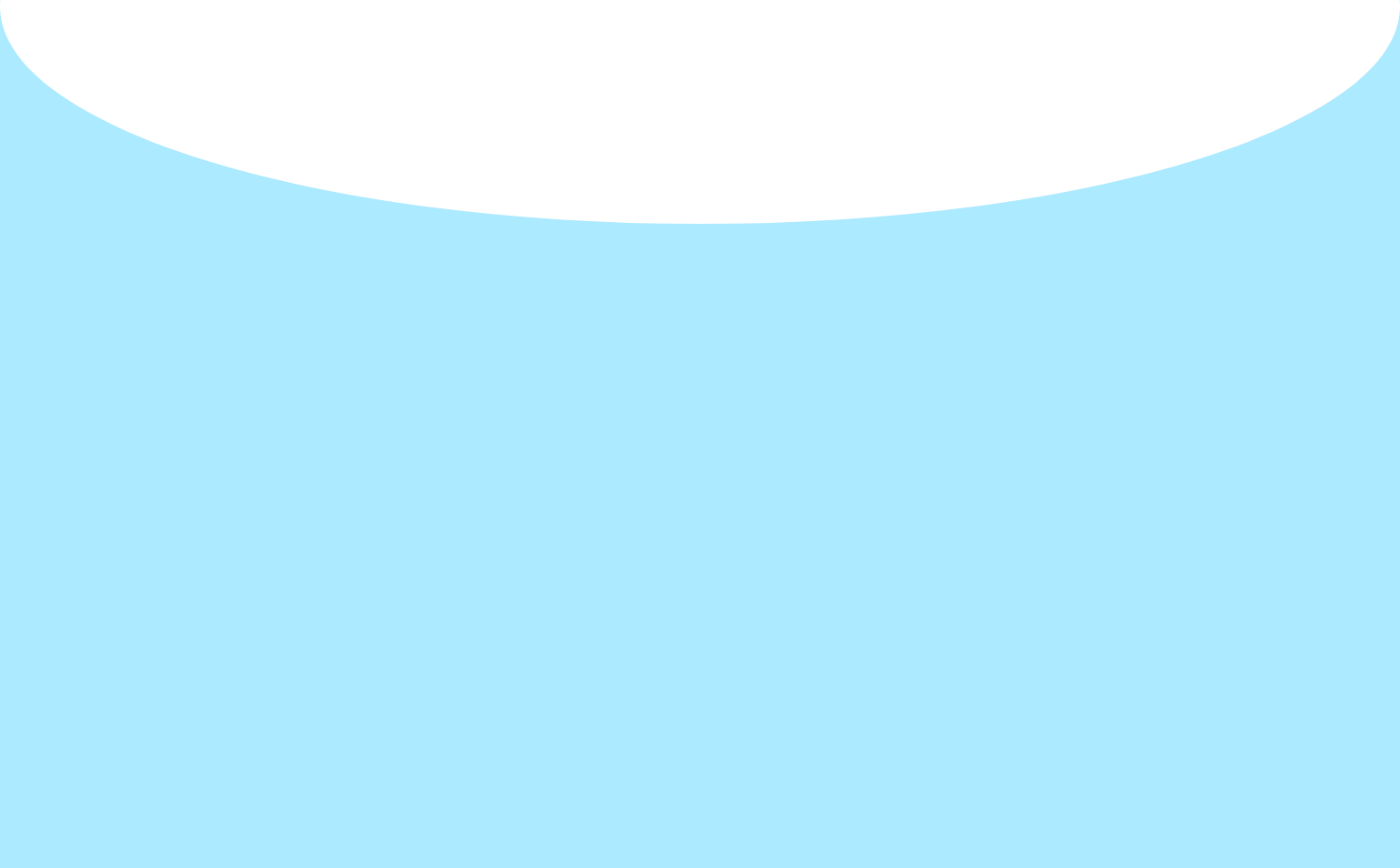「市役所の未来を描く」—自治体職員と共創した前例なき改革
地方自治体の庁舎建て替えは、単なる建物の更新ではありません。それは市民サービスのあり方を根本から見直し、未来の姿を描く絶好の機会です。KPMGコンサルティングのガバメント・パブリックセクターが中心となって進めた本プロジェクトでは、人口約17万人の基礎自治体の新庁舎建設において、従来の「建物ありき」の発想を覆し、職員の想いと市民の視点を中心に据えた革新的なアプローチを実践しました。本記事では、多様なバックグラウンドを持つコンサルタントたちが、どのように職員の発想を解き放ち、テクノロジーと人間らしさが融合した新しい窓口サービスを創造していったのか、その現場の生の声をお届けします。
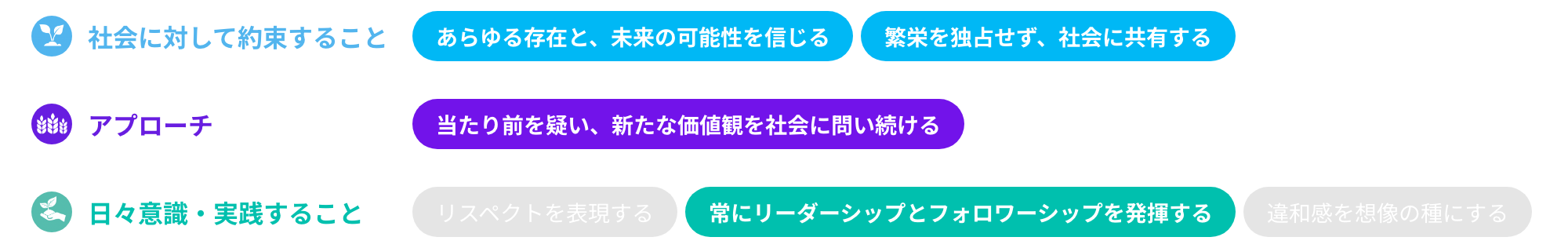
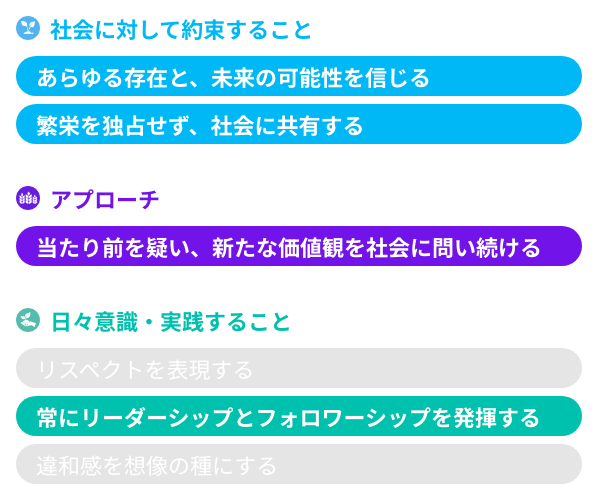
KPMGコンサルティングメンバー

K. S

H. O

A. Y
今回のプロジェクトについて教えてください

K. S
KPMGコンサルティングメンバー
従来は建物という「箱」ができてから、その中でどう業務を行うかを考えるという流れが主流でした。しかし今回は、まず理想の窓口業務を考え、それが叶う建物を設計したい、というクライアントの思いがありました。とは言え設計には物理的な制約はあるので、建物の基本設計というハードと窓口業務というソフトを並行して検討し、相互にフィードバックしながら進めるというプロジェクトでした。

A. Y
KPMGコンサルティングメンバー
さらに、サービスデザインという新しい概念が出てきて、これは行政にはまだ十分に浸透していない考え方だったりするので、外部の専門家の知見を活用する機運が高まってきていると感じます。同市の場合、市長が先頭に立って改革を進めているという背景も素晴らしい点だと感じました。「ワークショップをして意見を出し合いたい」というのも同市からの要望で、どういう内容のワークショップにするかが我々の力の見せ所、という気持ちで臨みました。

H. O
KPMGコンサルティングメンバー
それに、今回は新庁舎で、箱がまだないプロジェクト。すでに箱があればその枠の中で考えればいいのですが、今回はゼロベースで発想を飛躍させて考える必要がありました。職員の皆さんにも、これまでの概念を壊し、飛躍してアイデアを出し合ってもらうためのワークショップなどを実施したのですが、日々の業務内容では、なかなか発想を飛躍する機会がないので考え方を変えなくてはいけないという課題がありました。さまざまなアプローチでそれを実現させるのが我々の使命でしたね。

ワークショップはどのような内容になったのでしょうか?


H. O
KPMGコンサルティングメンバー
まず市民の立場に立つということですが、職員は、自身が務める市役所や業務内容には詳しくても、利用者の視点を持って課題を出すのは難しい部分もあります。そこで、実際に利用者である市民として窓口での手続きを体験してもらいました。すると、今まで見えていなかった課題が次々と浮かび上がってきました。例えば「隣の人の相談内容が聞こえてしまう」「ついたてがなく顔が見え、プライバシーが守られていない」など、これは利用者の立場だったら嫌だ、といった率直な感想が出てきました。業務をしている側にとっては日常で「当たり前」の光景ですが、実は市民にとっては課題であるという部分が可視化されました。ワークショップは主にA. Yさんに担当してもらいましたが、意見を出しやすくする仕掛けを作っていましたね。

A. Y
KPMGコンサルティングメンバー
そういう工夫もあってか、ワークショップは非常に活発な意見交換の場となりました。30代の職員を中心に実施したのですが、普段から横の繋がりはあるとはいえ、部署を超えて庁舎の未来について話をするというような機会はなかったので、このワークショップ自体が新鮮な体験だったようです。

生き生きと意見を交換している姿が目に浮かびます。プロトタイピングについても教えてください


H. O
KPMGコンサルティングメンバー
例えば、メッセージアプリを用いた申請システム。いくつかの地方自治体でも導入されているので、耳にしたことがある職員もいましたが、どういったものなのか、メリットもいまいち分からないという状態。だけど動く画面で体験すると「なるほど!」と理解が何段階も深まります。実際に動くものを触ってもらうことで、「こんなこともできるのか」という発見が生まれ、そこから「じゃあこれもできるんじゃないか」と発想が広がっていきました。

K. S
KPMGコンサルティングメンバー

H. O
KPMGコンサルティングメンバー

職員の方々からはどのような意見が出てきたのでしょうか?

A. Y
KPMGコンサルティングメンバー
確かにロボットによる案内や、AIを活用した業務効率化のアイデアも出ました。しかし、それ以上に多かったのは「市民と直接対話することの重要性」を訴える声だったのです。

K. S
KPMGコンサルティングメンバー

H. O
KPMGコンサルティングメンバー
異なる意見の橋渡しが、全て1つの解に導けるわけではありません。実際には建物の設計上の制約もありますし、「制約条件が明らかになったとき、改めてどちらを選べばいいかを議論しましょう」という形で落ち着くこともありました。重要なのは、さまざまな視点があることを皆が認識し、それを次のステップにつなげること。ですから、対立する意見も豊かな議論の種になりますし、異なる意見を出し合える場を作ることが我々の仕事でもありました。
最終的には、これらの意見を集約してスケッチ図という形にまとめてご提出したのですが、これは単なる絵ではなく、職員の想いや考えを具現化・可視化したものです。設計業者に「私たちはこういう窓口を作りたい」と分かりやすく伝えるためのツールになります。

今回のプロジェクトチームの構成と、それぞれの強みをどう活かしたのか教えてください


K. S
KPMGコンサルティングメンバー
この多様性は偶然ではないんです。採用においても応募者の方々が各々の現場で培ってきた知見や強みを重視し、多様な方々に仲間になっていただく。その前提の上で、プロジェクトごとにそれぞれの個の力を持ち寄って最適なチームを編成しています。

H. O
KPMGコンサルティングメンバー

A. Y
KPMGコンサルティングメンバー

K. S
KPMGコンサルティングメンバー

H. O
KPMGコンサルティングメンバー

A. Y
KPMGコンサルティングメンバー

最後に、これから共に働きたい方はどんな方でしょうか

H. O
KPMGコンサルティングメンバー
「自治体が起点になって街を作っている」という面は実際大きいですし、自治体や行政だから救える人がいます。私たちの提供するコンサルティングを通じてその自治体や行政が元気になり、職員がやりがいを持って働ける環境を作りたい、その結果として市民の生活も良くなっていく。そんな好循環を生み出していきたいと考えています。そういった、同じ想いの方がいたら一緒に働きたいですね。

A. Y
KPMGコンサルティングメンバー
あと、自分以外の存在をちゃんと考えられる人は素敵ですね。プロジェクトで関与するクライアントや、ステークホルダーは多様です。例外的なケースや、マニュアルに当てはまらないことも想像して、柔軟に対応策を考えられる人と一緒に働きたいと感じています。

K. S
KPMGコンサルティングメンバー
今回のプロジェクトでは、良い形を体現できたと思っています。私たちが考える課題や答えを押し付けるのではなく、職員自身が考え、課題を発見できる場を作ることに注力しました。単に他の自治体の事例を紹介するだけでなく、実際に窓口体験をしてもらうことで、市民目線で考えることを促し、プロトタイピングによって創りながら考え、検討することを体感してもらい、自分たちで感想を言い合って合意を形成していく。こういう支援の形を作り上げられる人、クライアントと伴走できる人と働きたいですね。
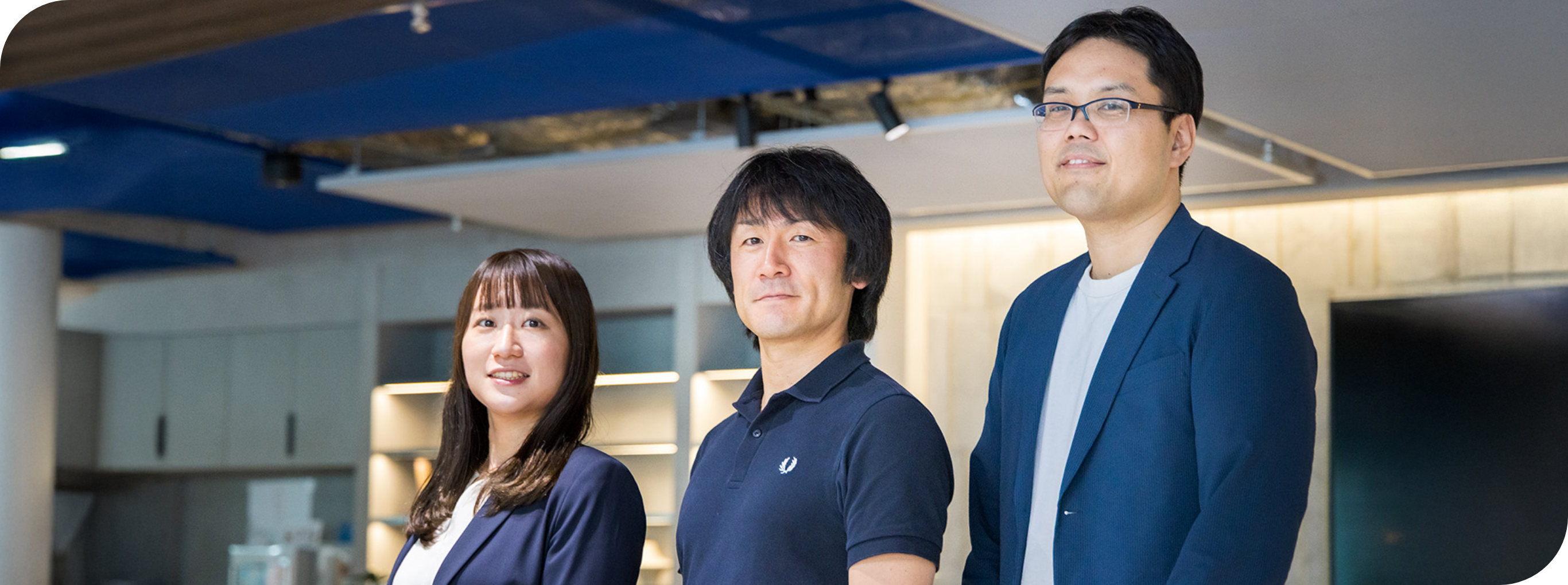
※記事の記載内容は2025年8月時点のものとなります。